お金を表す「代・賃・料」
2018年1月29日 TV
「○○代」は、モノの代わりに支払うお金
「○○賃」は、人に何かやってもらったことと引き換えに支払うお金
「○○料」は、一定に決められた金額かどうか
それぞれどのように使われ始めたかによって意味が異なる。
〇「○○代、○○賃、○○料」の語源。
「○○代」は、「代金」。「○○賃」は、「賃金」。「○○料」は、料金」。
〇「代金」という言葉は、どのようにして使われ始めたのか?
江戸前期に使われるようになった。井原西鶴『日本永代蔵』には「代金」と書かれている。
「代金」とは、モノの代わりとして支払うお金、ということ。
そこで、食事の代わりに支払うお金は「飲食代」、書籍の代わりに支払うお金は「書籍代」となる。
〇「賃金」という言葉は、どのようにして使われ始めたのか?
江戸中期に使われるようになった。「賃」とは、訓読みで「賃(やと)う」と読む。
つまり、「賃金」とは、人に何かをやってもらったことと引き換えに払うお金、ということ。
そこで、大家さんに家を貸してもらったことと引き換えに支払うお金は「家賃」、運転士さんに電車に乗せてもらったことと引き換えに支払うお金は「運賃」となる。
〇「料金」という言葉は、どのようにして使われ始めたのか?
明治時代に使われるようになった。
郵便局が誕生したことで、初めて料金という言葉が使われた。それまでの飛脚は言い値で決まっていたが、郵便局になってから、重さや大きさで値段がきまるようになった。
「料」とは、訓読みで「料(はか)る」と読む。つまり、「料金」とは、重さや大きさを料(はか)って、一定に決められている金額のこと。
そこで、大人、子どもの値段が決まっている遊園地は「入園料」、授業を受けるのに決まっている学校は全員に一定に決められているため「授業料」となる。
「○○賃」は、人に何かやってもらったことと引き換えに支払うお金
「○○料」は、一定に決められた金額かどうか
それぞれどのように使われ始めたかによって意味が異なる。
〇「○○代、○○賃、○○料」の語源。
「○○代」は、「代金」。「○○賃」は、「賃金」。「○○料」は、料金」。
〇「代金」という言葉は、どのようにして使われ始めたのか?
江戸前期に使われるようになった。井原西鶴『日本永代蔵』には「代金」と書かれている。
「代金」とは、モノの代わりとして支払うお金、ということ。
そこで、食事の代わりに支払うお金は「飲食代」、書籍の代わりに支払うお金は「書籍代」となる。
〇「賃金」という言葉は、どのようにして使われ始めたのか?
江戸中期に使われるようになった。「賃」とは、訓読みで「賃(やと)う」と読む。
つまり、「賃金」とは、人に何かをやってもらったことと引き換えに払うお金、ということ。
そこで、大家さんに家を貸してもらったことと引き換えに支払うお金は「家賃」、運転士さんに電車に乗せてもらったことと引き換えに支払うお金は「運賃」となる。
〇「料金」という言葉は、どのようにして使われ始めたのか?
明治時代に使われるようになった。
郵便局が誕生したことで、初めて料金という言葉が使われた。それまでの飛脚は言い値で決まっていたが、郵便局になってから、重さや大きさで値段がきまるようになった。
「料」とは、訓読みで「料(はか)る」と読む。つまり、「料金」とは、重さや大きさを料(はか)って、一定に決められている金額のこと。
そこで、大人、子どもの値段が決まっている遊園地は「入園料」、授業を受けるのに決まっている学校は全員に一定に決められているため「授業料」となる。
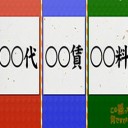

コメント